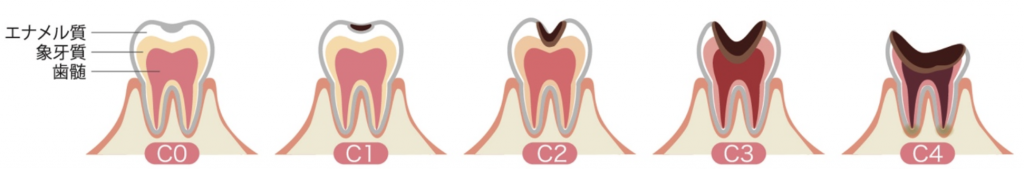
むし歯は「ムシバ菌が起こすもの」と思われがちですが、原因はそれだけではありません。最新の研究では「特定の菌の仕業」ではなく、プラーク内に暮らす多様な菌の「バランスの乱れ」がむし歯発生の大きな要因であることが明らかになっています。
今回はこの新しい視点から、ムシバ菌の種類や特徴、発生のメカニズムなどをご紹介します。
ムシバ菌は1種類じゃない?代表的な菌とその特徴
お口の中には数百種類もの細菌が住んでおり、普段は「プラーク」という集合体の中で互いに共存しながら静かに暮らしています。そのなかには、食べ物に含まれる糖をエサにして「酸」をつくり、歯を溶かしてしまう菌が存在しています。これが、いわゆる“ムシバ菌”とよばれる細菌です。むし歯にかかわる菌は複数あり、それぞれが異なる役割を持って進行を後押しします。
ここでは、代表的な3種の菌をご紹介しましょう。
1、ミュータンス菌(Streptococcus mutans)
“ムシバ菌”の代表格となる菌です。
飲食物に含まれる糖をエサにしてネバネバ物質(不溶性グルカン)をつくり、歯の表面にしっかりとくっつきます。さらに、プラーク内では酸を作り続け、エナメル質をゆっくり溶かしていきます。
2、ソブリヌス菌(Streptococcus sobrinus)
ミュータンス菌と並ぶ代表的な菌です。
ミュータンス菌よりも強力なネバネバ物質を作って、他の細菌たちを呼び寄せます。ミュータンス菌・ソブリヌス菌の両方がそろうとプラークはより頑丈になり、むし歯リスクが一気に高まります。
3、ラクトバチルス菌(Lactobacillus属)
初期のむし歯の“穴”に入り込み、そこからさらに歯を溶かしてむし歯を奥へ広げる菌です。
ミュータンス菌やソブリヌス菌のようにネバネバ物質は作らないため、つるつるした表面ではあまり見られません。そのかわり穴や溝、くぼみなどで活動し、むし歯の悪化に一役かっています。
「ムシバ菌」だけじゃない? むし歯発生に必要な4条件
むし歯は「ムシバ菌さえいなければ防げる」と思われがちですが、その発生にはもっと複雑なメカニズムが関わっています。むし歯になる過程では「ムシバ菌」のほかに「宿主」「糖分」「時間」が必要で、これら4つの条件がすべてそろったときにむし歯が起こると考えられています。
宿主(歯・唾液)
歯の質や形、唾液の量と質は、人によって異なります。
例えば、唾液はムシバ菌が作る酸を中和し、歯を修復する重要な役割を持っており、量が少ないとむし歯リスクが高くなります。
糖 分
ムシバ菌は糖分をエサに、むし歯の原因となる「酸」や「ネバネバ物質(不溶性グルカン)」を作ります。とくに、「砂糖」は酸を作るスピードも量も大きく、むし歯リスクを高めます。
糖 分
糖分を摂るとお口の中は酸性になり、その状態が長く続くほど歯は溶けやすくなります。
「ダラダラ食べ・ダラダラ飲みが危険」といわれるのはこのためです。
いかがでしたでしょうか。次回は虫歯ができるメカニズムと防ぐ習慣をご紹介いたします。
